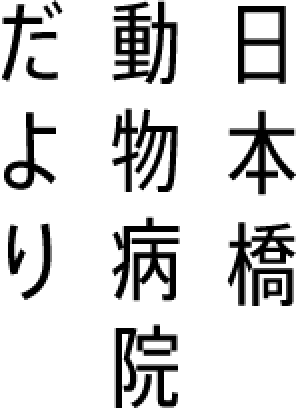眠れない日もある – 犬の肝臓がん –
秋らしくなってきました。朝晩も寒いくらいの日があります。とても過ごしやすい季節になりました。
今回は、獣医師の眠れない日々、いや、犬の肝臓の手術について書いてみます。
体重が10kgを超えるワンコの話です。水をたくさん飲んでトイレが近い、そんな病気を検査しているときに、お腹の超音波検査、いわゆるエコー検査をしているときのこと、肝臓の異常を発見しました。
肝臓のデキモノは鶏の卵くらいの大きさで、できている肝臓の部位から肝臓癌の疑いがあります。飼い主さんにお話をして、まずはCT検査で詳細を確認し、詳細を把握したあとで肝臓のデキモノを取ることになりました。
肝臓の手術は、獣医師にとって難易度の高いものです。一人よりは、二人以上の慣れた獣医師が息をあわせておこないます。
では、何が難しいのでしょうか。血管処理の多様性です。
肝臓の手術は、肝臓の血管処理にかかっています。肝臓に入り込む血管と、肝臓から出る血管、肝管の処理を行うことが、肝臓手術のほぼ全てです。
この処理するべき血管は、肝臓の解剖をしっかりとわかっていれば、大筋は問題ないのですが、それぞれの犬によって微妙な違いがあることが初学者を悩ませます。
例えるなら、落とし穴は普通こことここにありますよ、でも、他にもあるかも知れませんよ、落ちずにゴールまで進んでくださいね、落ちたら取り返しがつかないことがありますよ。こんな感じです。
誰も落とし穴に落ちたくはありません。慎重に慎重を重ねて進みます。手術は基本操作の繰り返しと言えばそうですが、何かあったときのリカバリーができないことがあり、そのため経験のある獣医師へと、予めバトンが渡されることになります。
その点僕は、肝臓手術の専門ではありません。肝臓手術は任せてくださいと言うつもりはありません。今回は、事前の検査結果で、安全で確実に成功できるという手術計画を持っているだけです。予想外のことが幾重にも起こらない限り手術は問題なく終わるでしょう。
飼い主さんの期待に応えたい一心で手術に臨みます。このときに大切にしたい思いは、一定水準、合格点以上の技能を持って引き受けるということです。
一般的な獣医師が行う手術は多岐に渡ります。1か月以内に行った手術は、一般的な避妊手術や去勢手術の他に、骨折の整復手術、脾臓腫瘍の摘出、膀胱癌の摘出、乳腺腫瘍、膝の靭帯損傷の骨切り手術、口の中にできた腫瘍の手術、まぶたの腫瘍、皮膚癌の切除、胃腸の手術などなどです。
たった1か月でも、こんなに多くの手術をしているという話ではなく、守備範囲が広い分、それぞれの手術件数は多くはありません。それぞれの手術は、数多く行うほどに上達するものです。
もしも、1か月のうちに骨折の手術だけを毎日やれたら、相当な力がつきます。しかし、骨折手術の専門病院でない限り、毎日骨折手術を行っている獣医師はいないでしょう。
特に僕のように、一般的な動物病院の獣医師の場合、1年に1度くらいしか行わない手術もあります。また、動物病院で30年近くを過ごしていますが、初めて行う手術もあるわけです。
長くなりました。お伝えしたかったことは、一定水準で仕上げる必要がある高難易度の手術でも、頻度が低いと毎回新鮮な緊張があるということです。手術日が決まったら、ひたすらシミュレーションを繰り返します。今回は、肝臓の手術でしたので、お肉屋さんでレバーを買ってきて、イメージトレーニングをすることができました。他の手術では、今回のようなシミュレーションはできませんけど。素材がスーパーで手に入らないので。
これまで何度も来院された犬と飼い主さん。うちの動物病院で手術を希望された、その思いに懸命に向き合う。
眠れない日もあります。
超音波検査の画像を精査し、CT画像から注意する箇所を確認し、手術中の想定外をできるだけ多く挙げながら備える。この同じことを何度も何度もイメージします。
とても便利だと思うのが、TouTubeです。国内外の獣医師が、手術動画をアップしていて、解説まで付いている。ただ、無料のTouTubeだからか、肝心なところはカットされていることが多く、詳細まではわからない。国によって、獣医師によって、手術のやり方が違うのも興味深いところです。
Toutube動画では、手術台の上で展開される手術とともに、背景の整体モニタや電気メスの電子音が聞こえてきます。この音は没入感をとても促し、観ている僕の心拍数を緊張へと一気に高めてくれ、他の何よりも手術のイメージトレーニングには効果的です。
手術当日になりました。ワンコをカートに入れて連れて来られたお母さんの顔は、とても心配そうです。このような場面で心配しない方はいないでしょう。僕も笑顔でお迎えし、大まかな流れをお話して、ワンコを預かりました。
ジェットコースターに例えると、シートに座って安全ベルトを締めた状態です。ワンコも僕達も、飼い主さんも。
手術の時間になると、まずは血管確保という処置をして点滴を開始します。ゆっくりと麻酔薬を注射し、呼吸を補助するための気管挿管、手術中に麻酔を維持するための吸入麻酔と、この段階までくると、ジェットコースターは最高点に向けて上昇中です。
手術のための手洗いを済ませ、アルコールを手に擦り込んで、手術着に着替えグローブをつけます。既に麻酔がかかり、手術部位の毛刈りと消毒が済んだワンコが手術台に仰向けになっていて、助手、麻酔係、周りのスタッフに開始の声をかけてスタートです。
切開し、小さな出血も確実に止めながら、お腹を開くと見えてくる大きな脂肪の塊を綺麗に取り除くところまではいつもどおりに進んでいきます。切開したお腹を器具を使ってぐいっと広げて見えてくるのが、目的とする肝臓です。
今回は、この肝臓にできている腫瘍を取り除きます。とても簡単に言えば、腫瘍のついた肝臓の一部を切り取ることが、今回のミッションです。
肝臓の腫瘍と、同じく肝臓の中にある注意するべき血管は、肝臓を外からいくら観察しても見えるものではないので、CT画像をイメージしながら慎重に切っていきます。
肝臓の中には、まるで網目のように血管が広がっていて、肝臓を切るときに主要な血管を不用意に傷つけてしまうと、予想しなかった出血が起こり危険です。
突然ですが、ヘチマたわしをご存知でしょうか。ヘチマの繊維は、立体的な網目状態になっています。これが肝臓の血管のイメージに近いものです。ヘチマたわしを丸ごと寒天で固めて、繊維をできるだけ傷つけずに切断する。これが実際に近い例えです。
この切断で活躍する機器に、超音波乳化吸引装置があります。これは、肝臓の血管などをできるだけ残して、それ以外の組織を柔らかくして吸い取るものです。先ほどのヘチマ寒天の例でいいますと、ストローで寒天だけを吸い取り、ヘチマの繊維を露出する。そうして、露出した繊維だけを処理して切断すれば、安全に肝臓を切断することができます。
手術を安全に行うには、まあ、これは手術だけには限りませんが、一見危険な手技を展開する場合には、幾重にも安全策を用意しておかなければなりません。偶然に期待しないことです。
かつて、獣医学部ではなく医学部にある大学病院の消化器外科で肝臓がんの手術について勉強させてもらったことがあります。患者さんは、高齢男性でした。医学部の医局は朝が早く、早朝からお医者さん達がカンファレンスという、その日に予定されている手術の事前検討会が行われます。先生方は、おそらく毎日のことでしょうから、大枠を確認することで、理解されているようでした。
実際に手術を見学させていただき、手術手技の詳細を目の当たりにしてわかったことは、偶然に期待しない。幾重にも安全策を講じるということでした。そのために、ここの先生方は、手術機器にできるだけ頼らず、細かな血管も手作業で処理していきます。具体的には、1cmくらいずつ肝臓に切れ込みを入れ、そこに露出する血管を全て糸で括る方法です。それもとても迅速に進んでいきます。
手術に対する安全策についての学びは、僕の手術の基礎になりました。今回は、まさに肝臓の腫瘍。とにかく丁寧にを心がけて慎重に肝臓を切っていきます。肝臓の切断面の真ん中に、特に大きな血管があるので、両端から真ん中に向かって攻めていき、最後に真ん中の最も重要なところを処理する計画です。
医学部では、鉗子という器械を使って肝臓を1cmほど挟むことで、肝臓の細胞を脆くし、残った血管などを糸で括る。これを1回の手術で200から300回ほど繰り返していました。犬の肝臓は、鉗子で挟むと切れてしまう血管があり、人の手術と同じように犬の手術をすることはできません。
今回は、超音波吸引機で肝臓の細胞を吸引し、残った血管などを糸で括ったり、超音波メスでシールしたりして進めました。超音波メスも万能ではありません。超音波メスが使える血管には、太さの制限があります。太い血管だと、超音波メスで止血が十分にできないこともあるために、最後に現れる太い血管は超音波メスを使わずに、しっかりと糸を使って結紮しました。
この糸を出血させることなく安全に結ぶことができたら全てが終わる。肝臓腫瘍を取り終える。その思いで、最後の太い血管をゆっくりと結紮しました。
腫瘍のついた肝臓を切り離し、出血がないことを確認し、記録のための写真を撮ったら、あとはお腹を閉じます。このあたりで、やっと僕の心拍数が正常に戻ります。お腹を閉じていくときも、数回は出血がないかを確認し、最終的に皮膚を縫って手術を終えました。
手術が終わり、麻酔から覚めるまでの時間は、おおよそ5分ほどです。ワンコは順調に目を覚ましてくれました。手術も麻酔からの覚醒も問題はありませんでしたが、手術後2-3日は注意が必要です。数日間は入院してもらって、しっかりとみることになっています。
ところが、このワンコは手術後すぐから、とっても元気です。お部屋から出たいように見えますし、手術後まだ数時間なのに、走り出そうとします。この様子では、入院よりは自宅の方が安静にできそうでした。飼い主さんに、術後の様子を報告し、少し長めに予定していた入院期間を短縮することを提案すると、ご家族は驚かれています。2泊3日の入院で健康管理をして3日目に退院することになりました。
お迎えに来られたお母さんは、少し不安そうに見えます。手術が終わったばかりなので、もう体力的には回復しているのか、急に体調が悪くなったりはしないか、そのような心配は当然のこと。ワンコのとても元気な様子に戸惑われながらも、緊張が解れたようでした。ここから何か問題が起こることはないでしょう。
その後、定期検診や抜糸が順調に終わっていき、今回の予定していた一連の流れは無事に終了しました。
思うことがあります。もし毎日こんな手術をしていたら、もっと経験値も上がり、眠れないこともなくなるのだろう。しかし、僕は専門的に一つの分野だけに特化することよりも、子犬から高齢になるまでの間、かかりつけとしてお役に立ちたい、そんな想いをもっています。これは開院以来、一貫したものです。
犬が年を取り、看取りについてお話をする段階で、ふと、最初の診療記録をみて「生後3か月」などと初診のときの月齢が書かれているのを見ると、迎えられてからお別れの日まで、関わることができたことに感慨を覚えます。ご家族にも、その診療記録の表紙に書かれた「生後3か月」を見てもらったり、そのときの体重をお伝えしたりすると、お互いに自然な笑みがこぼれます。
今回のワンコは、やや高齢。それでも、この手術で寿命はかなり伸びたはずです。犬との生活では、ご家族も犬も、癒し癒される関係。できるだけ長く一緒にいられるように願っています。